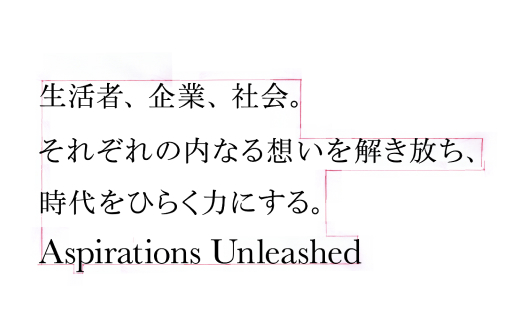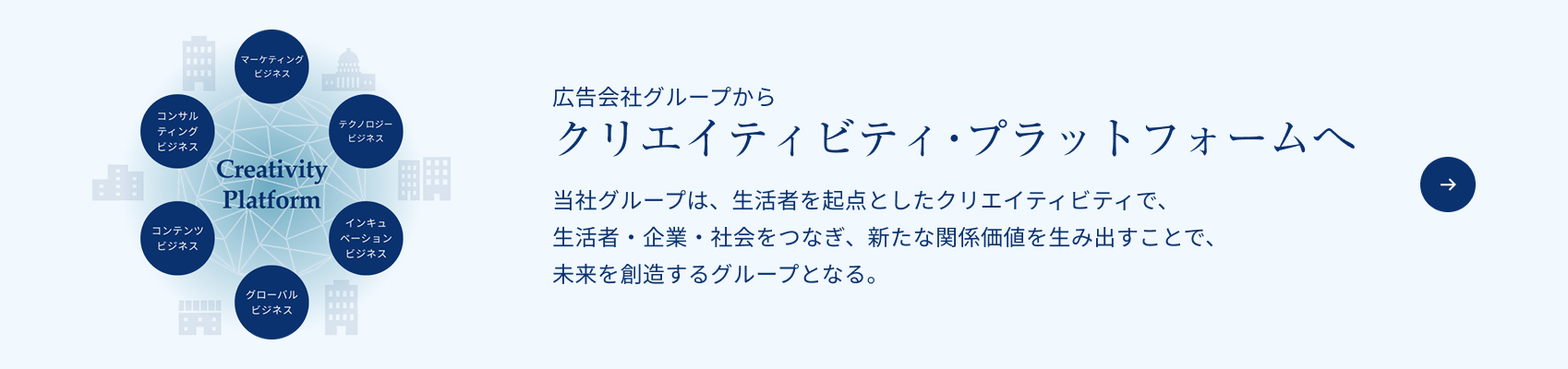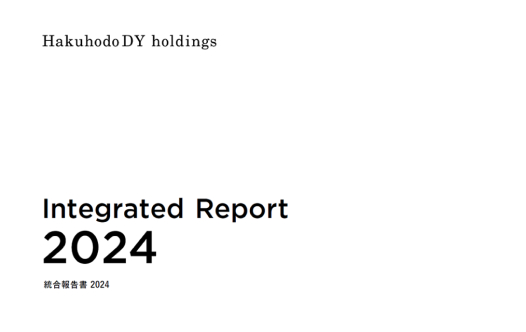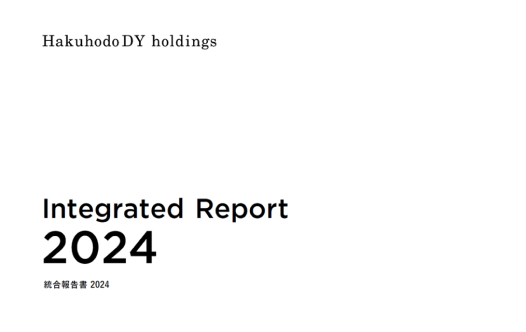博報堂キースリーは、カルビーの新規事業を担う「Calbee Future Labo」と共に、2023年からカルビー商品のデザインやキャラクターIPを活用した、「NFTチップス」や「WEB3 GAME FES」、「はぴウェル応援団」といったさまざまなweb3キャンペーンを実施してきました。
2025年4月には二次創作における外部クリエイターの与信管理やライセンス業務を簡素化し、IP事業の課題解決を目指すIP管理プラットフォーム『かるれっと』 を発表しました。さらに、この取り組みを進化させるため、カルビー商品のタベオト(食べる際に生まれる音)をIPととらえて、タベオトを使った楽曲を創作する音楽レーベル『じゃがレコード』 を共同で設立しています。
本取り組みの背景や目指す未来について、Calbee Future Labo ディレクター
の松本 知之氏、第一弾楽曲「DAHA」を制作したクリエイターユニット、niKuのコンポーザーChinozo氏、博報堂キースリーの佐野の3名に話を聞きました。
(写真右から)
松本 知之氏
カルビー株式会社
Calbee Future Labo ディレクター
Chinozo氏
niKu コンポーザー
兼 ボカロP
佐野 拓海
株式会社博報堂キースリー 取締役 兼 博報堂 オープンインキュベーション局
チーフプロデューサー
web3はあくまで手段。どのようにマーケティングへ活かすかが重要
── はじめに、2025年4月にカルビー初のブロックチェーン技術を活用したIP管理プラットフォーム「かるれっと」を発表した経緯を教えてください。
松本
カルビーでは以前から、デジタルネイティブ世代に向けたマーケティングへシフトしていく必要性を感じていました。Calbee Future Laboが新規事業を検討する際も、既存ブランドがお客様の生活にさらに浸透していく領域にこそ、多くのチャンスがあると考えていたのです。
その一環として、NFTを活用したキャンペーンや、農業体験ゲーム「Astar Farm」とのコラボ企画など、web3領域での取り組みを積極的、能動的に実施してきました。個人的には、「web3やNFTとは一体何なのか」というところからスタートしたのですが、博報堂キースリーからweb3事業者の方々をご紹介いただき、実際にお客様からの反応が見えたことが大きな転換点になりました。
重要なのは「web3はあくまで手段であり、どうマーケティングに活かしていくか」という点です。そうしたなかで、カルビーの各ブランドや企業のブランドを、食べること以外の形で生活者であるお客様に価値を感じてもらうためには、ブランドをリデザインしたり、二次創作を促進したりすることが重要だと考えるようになりました。
その際に課題となるのが、ブランド利用に関する与信管理や権利管理です。これらを透明かつ効率的に進めるために、ブロックチェーン技術を活用した「かるれっと」という仕組みを開発しました。
「かるれっと」を通じて様々な創作活動が生まれ、究極的には一般のクリエイターがカルビーのブランドを自由に活用し、多様な作品を生み出していただけるような世界を目指して設計しています。

── そのようなお考えに至ったのは、どのような背景があるのでしょうか?
松本
従来、商品はメーカーが作るもので、中身の設計からパッケージデザインまでを手がけるのが当たり前でした。しかし、現代は個人のSNSや動画配信サービスなどを通じた創作活動が盛んに行われています。
そのため、メーカーとして「この商品をぜひ食べてください」という提案の姿勢は変わりませんが、マーケティングのあり方ももっとお客様に寄り添い、企業活動にお客様も参加していただけるような形を目指すべきだと考えています。
例えば、「じゃがりこ」をさりげなくデザインした国産スニーカー「じゃがりこ と」スニーカーでは、二次創作の要素が強いデザインだったにもかかわらず、多くの人から「かわいい!」という非常にポジティブな声をいただきました。
また、「カルビーレトロ」というレトロ調のデザインを使った際には、ベビー服のロンパースに採用されたりするなど、当初は想像もできなかった分野にも広がりを見せています。このような二次創作的な動きについて、「カルビーらしさ」は残しつつも、新しい魅力的な形に変換されていることが多く、ここにマーケティングにおける大きな可能性があると感じています。
個人クリエイターの自由なIP活用をDID/VCで促進
──さまざまなweb3キャンペーンを実施したなかで得られた発見はありましたか?
佐野
松本さんも仰っていた「能動的」というキーワードが、web3領域の一連の取り組みを象徴するものだったと思います。自分たちから積極的に動かなければ、こうしたコラボレーションは実現しなかったわけですし、特にゲーム業界の方々からすると、カルビーはこれまでコラボレーションの候補に挙がっていなかったのではないでしょうか。だからこそ、異業種コラボレーションによる意外性が話題となり、結果として大きな盛り上がりに繋がりました。
これまで接点のなかった業界に私たちから積極的にアプローチすることで、意外な親和性や成果を見出せたりと、従来のIPコラボとはまた違った新しい価値を生み出せている感覚があります。そういう意味でも、まだまだ開拓の余地がありますし、業界・業種を超えたコラボレーションの可能性が広がっているのを感じていますね。

── IP管理プラットフォームに、DID(分散型ID)とVC(デジタル証明書)を採用した理由をお聞きしたいです。
松本
私たちのチーム構成は少し特殊で、IPの接点を魅力的なデザインやプロダクト、コンセプトとして作り出すデザインチームと、それをバックエンドでデジタルに実装する仕組みやシステムをつくるCXチームが連携しています。「かるれっと」のシステム開発においては、当然ながら色々な苦労がありましたが、チーム内には「お菓子作りはできないけれど、デジタルシステム設計には長けている」という異質なメンバーが在籍していて、そのメンバーを中心に開発を進めていきました。
最終的にDID/VCを採用した理由は、将来的に個人のクリエイターの方々が弊社のIPをより容易に活用できるようにするためです。今まで企業のIPを個人が利用したい場合、企業に直接問い合わせし、利用許諾を得るのはハードルが高く、実際に行動に移せる人はほとんどいなかったと思います。そのため、「かるれっと」では個人が制作した二次創作のデザインを、我々が提携しているライセンシー企業に開放し、実際のビジネスとして展開できるように設計しています。
これらは収益の一部をクリエイターに還元する仕組みとして安全に、そして信頼性を持って運用する必要があり、そのためには個人の認証(KYC)やプライバシー管理の技術が不可欠です。そこで、個人情報を必要以上に開示せず、なおかつ確実に本人確認ができるDID/VC技術の導入が適していると判断しました。
とはいえ、この取り組みに関しては、前例となる明確なユースケースが存在しませんでした。それこそ既存のライセンシー企業やキャラクターIPを管理する企業の方が、本来であれば今回のようなシステムを構築するのが自然かもしれません。
しかし、「個人のクリエイターが、カルビーの企業活動に主体的に参加できる仕組みを作りたい」という思いが根底にあるからこそ、私たち自身が取り組む意義があると考えていました。これから先、この仕組みの上にどのような新しい価値を生み出していけるかが最も重要なポイントだととらえています。
長年こだわってきた「タベオト」に着目した楽曲制作の舞台裏
── さらに直近では、タベオト(食べる際に生まれる音)を使った楽曲を創作する音楽レーベル『じゃがレコード』を共同で設立しました。こちらは、どのようにしてプロジェクトが始まったのでしょうか?
松本
カルビーは昔から、CM制作においてもタレントさんが「パリッ」とスナック菓子を食べる音に徹底的にこだわってきました。人がポテトチップスなどを食べているときの「カリッ」「パリッ」といった美味しそうな音が鳴ることで、「食べたい」という気持ちを喚起することは、商品の魅力を伝えるうえで非常に重要です。
カルビーの強みとしては様々な商品のバリエーションがあり、ポテトチップスだけでもカットや厚さ、製法が異なるため、それぞれ独自のタベオトを生み出します。このように、タベオトはカルビーにとって生命線であり、「お客様にカルビーの美味しい音を届けたい」という思いから、何か新しい形でタベオトを活かせないかと考えていました。

そんな中、カルビーのブランドやデザインがIPとして活用されるケースがある一方で、SNS上で投稿されている「『じゃがりこ』を使ってポテトサラダを作る」といったレシピ投稿も、ある意味で生活者(ユーザー)の二次創作とも言えるのではという話になったんです。同様に、タベオトも何らかの形でアウトプットを生み出せるのではないかと考え、チームの若手メンバーを中心に議論が始まりました。
正直、最初はよくわからないまま音楽スタジオに入り、試しにスナックを食べる音を録音してみたんです。私自身、趣味で音楽制作をやっていることもあり、収録したサンプリング素材を使ってリズムトラックを作ってみたところ、「これは意外に面白いかもしれない」という感触が得られました。そこで、このアイデアを佐野さんへ相談したのがきっかけになっています。
── Chinozoさんにお聞きしますが、タベオトを使った楽曲制作のお話をもらったときの心境はどのようなものでしたか。
Chinozo
今回、タベオトを収録して楽曲制作するために、色々な種類のポテトチップスを試食しました。その中でも薄切りタイプのポテトチップスが印象的な音を出してくれて、楽曲のアクセントになりましたね。また、楽曲内で優しく流れるパーカッションのような音も、ポテトチップスを食べる音を採用するなど、非常に面白い試みだったと感じています。
タベオトを音楽に取り入れるのはとても実験的なことで、通常ではなかなか難しいわけですが、今回は企業側から正式な許可をいただいて取り組めたので、純粋に楽しむことができました。
実は今回のコラボのお話をいただく前から、お菓子の音で何か面白いサウンドを作れないかと考えていたんですよ。その時に一番やりたかったのがパーカッションの音でした。これはどうしても入れたかったので、今回の楽曲「DAHA」にも絶対に入れたいと思っていました。
実際にSNSの反応を見ていても、「自分も使ってみたかった」というコメントをいただいたりと、タベオトに対して興味を持つクリエイターが意外にも多いことに気付かされましたね。

「開放性」と「権利保護」の両立を通じて新しいIPの展開を模索していく
── 音楽レーベルとして継続的にコンテンツを提供していく狙いはどこにあるのでしょうか?
松本
メーカーのマーケターとして、自社の商品に誇りを持ち、様々な提案を行うのは当たり前のことですが、実はもっと価値の広がり方そのものをもっと柔軟にとらえるべきだと考えています。必ずしもカルビーの商品を食べているお客様のみならず、最近は食べていないけれどカルビーのことを知っているお客様にどう思い出してもらうかという視点も重要です。そのアプローチの一つとして、お客様による創作活動のような形があってもいいと思っています。
むしろ、そうした創作のなかに私たちが思いつかない「クリエイティブ」が生まれるチャンスがある。イノベーションを生み出そうとするなら、メーカーが意図的に作り出すのではなく偶発的で面白いものを生み出す可能性のある層と繋がっていくことが、今の時代においては必要不可欠だと感じています。
佐野
実は当初から、音楽レーベルを立ち上げるという話だったわけではありませんでした。最初の発想としては「食べる」以外にも、「身につける」「持つ」といった接点をもっと増やしていこうという文脈があり、その中で「音」という新しい接点に注目したのが始まりです。
そこから「音」を切り口にするなら、プロのアーティストと組んで、食べる音を素材にした楽曲を作るというアイデアが出てきました。音楽事務所の方にも相談していくなかで、「音楽を自由に食べる」というコンセプトで活動しているクリエイターユニット「niKu」と出会い、プロジェクトが本格的に動き出したのです。
先ほどの「かるれっと」の話ともつながるのですが、松本さんが以前仰っていた「IPは守るものではなく、広げていくもの」という考え方が非常に象徴的だと思っています。一般的なIPライセンス管理を行う場合、IPは基本的に「守る」対象とされます。「かるれっと」のような仕組みを導入する際も、IP管理や契約の効率化や不正利用の防止といった発想が主な動機になると思います。
一般的な義憤がライセンス管理の煩雑さや非効率さから生まれるのに対し、カルビーの場合は「良いサービスは良い義憤から生まれる」という少し異なる視点を持っています。「多くの人が自由にIPを活用できる仕組みを作り、二次創作が自然に生まれる環境にする」といったように、IPをより開放し、広げていくという強い思いがカルビーの出発点になっているなと感じていますね。
従来、アーティストがカルビーとコラボレーションする機会といえば、テレビCMで楽曲を提供するくらいの接点しかなかったと思うんです。でも今回のように、一緒に楽曲を作ったり、タベオトを素材として取り入れるような形は、今までになかった新しい試みだと言えます。こういう取り組みこそ、プロだけではなく一般のアーティストの方々にも開かれていくような間口の広さにつながっていると思います。

── 最後に今後の展望をお聞かせください。
松本
「かるれっと」は最終的に多くのお客様が集うプラットフォームを構築することですが、その場から多様で面白いサービスや商品、楽曲などが生まれるかが重要な鍵となります。今後はいかに面白い価値を生み出すかに焦点を当て、様々な取り組みを進めていきたいと思っています。
佐野
タベオトをもっとオープンに活用できる仕組みを構築できればと考えています。たとえば、Chinozoさんのタベオトを唯一無二の価値を持つものだとして考え、それを多くの人が自由に使えるようにしていくというのは、とても面白い可能性を秘めていると感じています。
もちろん無断使用のようなケースは避けるべきですが、価値を生み出した本人にきちんと還元されるようにしていきたいと考えています。そのためには、ブロックチェーン技術を活用することで、誰が何を生み出したのかをきちんと記録し、追跡できるようにすることが非常に重要になってくると思っています。
「開放性」と「権利保護」のバランスを取りながら価値を広げていくことで、これまでにはない新しいIPの展開が見えてくるのではないかと非常に期待しています。
Chinozo
『じゃがレコード』の記念すべき第1弾の楽曲を担当させていただき、タベオトの魅力と可能性を知ることができました。今回のように食べる音を使ってこれからも創作活動ができればと思っていますし、タベオトで面白い作品を世に出していきたいですね。
『じゃがレコード』第1弾プロジェクトについてはこちら:
【対談】Calbee✖️ Chinozo 「ポテトチップス」で楽曲を作る? カルビーの音楽レーベルによる第1弾プロジェクト


松本 知之氏
カルビー株式会社
Calbee Future Labo ディレクター
1994年入社。営業、経営企画、ポテトチップスのブランドマネジャー、全社マーケティング戦略の立案などの業務に従事。2019年より4年間、マーケティング本部長を務め、2023年4月より現職。

Chinozo氏
niKu コンポーザー
兼 ボカロP
niKuとは別で個人での活動もしており、MV1.4億回再生の「グッバイ宣言」の作曲や、Adoさんへの楽曲提供も行っている。

佐野 拓海
株式会社博報堂キースリー 取締役 兼 博報堂 オープンイキュベーション局
チーフプロデューサー
主に生活者リサーチ、新規事業開発、新商品開発、ブランディング、サービスデザインなどの業務に従事。著書『DNVB生活者の義憤から生まれるブランド』。