誰もが注目する「Z世代」ですが、彼らに向けたマーケティング施策の多くが実は失敗に終わっているのではないか――。そんな疑問から、いまこそ「Z世代」を再考すべく、Z世代を研究する若手研究員、Z世代の企画屋、Z世代相手にビジネスを行う事業主の若手リーダー社員、Z世代を部下に持つ社員に登壇いただき、Z世代のリアルなインサイトを掘り下げます。
本稿では2024年10月16日~18日に開催されたアドテック東京2024にて行われたセッション「Z世代が語る「なぜ、Z世代向け施策は的外れなのか?」の模様をお届けします。

モデレーター
鹿毛 康司 氏
かげこうじ事務所代表
マーケター/クリエイティブディレクター
スピーカー
今瀧 健登 氏
僕と私と株式会社
代表取締役
定 絵里加 氏
株式会社学情
経営企画部 マネージャー 兼 インキュベーション室 室長
瀧﨑 絵里香
株式会社博報堂
研究デザインセンター 上席研究員
■自分が知らないことを知るからこそ、不安になり、綿密に情報収集する
鹿毛
今日は、言わば私たち上の世代がZ世代やその周辺の世代に教えを乞うセッションとなります。早速ですが定さんから順にプレゼンテーションをお願いします。
定
実際にZ世代と話をする中で出てきたキーワードに「就活の相談は就活で出会った人に」があります。コミュニティとかアルバイト、サークルなどではなく、インターンやOB訪問をきっかけに繋がった人たちにだけ、就活の相談を行うそうです。実際のコメントとして、「知り合いではない人に相談したい」「就活で出会った人に社会人を紹介してもらう」「エントリーシートを添削してくれるサービスを活用」などがありました。

瀧﨑
Z世代は気遣いをする世代でもあるので、友達や先輩などに相談するのは申し訳ないという気持ちがすごくあるとも聞きます。
今瀧
そもそも先輩に相談するという発想がなく、僕も就活で出会った人に就活相談をしていました。大学というセグメントに比べて、同じ就活で出会った人同士のほうがより細かくセグメントされているのもあると思います。
定
それから、「ワークライフバランスは40代になったら考える」「いざそうなった時にいろんな選択肢があるように、今は一生懸命働く」「そのためにも今は成長したい」という声や、さらには、「知らないことが多いから、このまま就活していいのかわからない」と悩む声もあります。そういう子たちがどうやって就活しているかというと、就活四季報を3種類買って、いいなと思った企業に付箋を貼り、ネットで調べて、それでもわからないことは中の人に聞くと。就活情報として出てるものだけではなく、統合報告書とか有価証券報告書、口コミサイトなど多方面から情報を集めて就活をしています。
鹿毛
そもそもZ世代は上の世代と一体何が違うんでしょうか。
瀧﨑
情報過多と言われる中で、自分が知らないことが多いことや、自分ができないことがあるとわかっているからこそさまざまな選択肢を求めるという...ある種の賢さというか、そうせざるを得ない側面もあるように思います。
今瀧
人生100年時代と言われ、ワークライフバランスも100年軸で考えなきゃいけないという側面もありますね。
■SNSの普及と共に拡がっていった「分人主義」
瀧﨑
日々、20~30人の大学生と一緒に研究する中、私たちが導き出したのが、「若者はもはやn=1で見られない」という事実です。これは「分人主義」という言葉ともつながると思っています。「分人」は平野啓一郎さんの著書で10年前に使われた言葉ですが、より現在、若者の共感を受ける言葉だと感じます。
昔は1人の自分が、仕事の顔、プライベートの顔とペルソナを使い分けるという考え方だったのが、今は、会社にいる自分、友達と一緒の自分、趣味の世界にいる自分...それぞれの自分を全て本当の自分と捉えている。この言葉が出てきたのが、まだSNSが出始めの2012年頃で、その後デジタル化によって、この傾向がさらに促進していったのかなと思います。

SNSを使いこなす若者だからこそ、人格が増えるきっかけ、分人主義に共感するきっかけが多い。彼らは「裏垢」ではなく「別垢」「専用垢」を使いこなします。どれかが裏の人格というわけではなくて、複数のアカウントすべてが本当の自分であるという意識です。実際、男子大学生で、趣味アカウントや高校までのアカウント、大学の仲間向けとインスタグラムのアカウントを5つ使い分け、さらにはTwitter(エックス)にも3つアカウントがあるという方がいました。彼にとってはそれぞれが独立した、大事なコミュニティになっている。また、ある女子高生は、母親から「お姉ちゃんなんだからもっとしっかりしなさい」と言われる日常に疲れてしまい、リアルと切り離したTwitterアカウントをつくったところ、そこでは自然と"妹キャラ"になれて、年上の人たちと会話を楽しんでいるということでした。
鹿毛
現実の自分とはまったく違う誰かに成り代わってみたいとか、誰しも思うことはあると思う。でも何かZ世代の特徴があるんでしょうか。
瀧﨑
土佐日記で「男もすなる日記というものを...」とあるように、昔から、自分と異なる人格のふりをすることで、いろいろな感情を露出しやすくなるということはあったと思います。デジタル化で、そうした"分人"をつくりやすくなったということはあると思います。
今瀧
僕もXで繋がってる人もいれば、Xは繋がってるけどインスタグラムが繋がってない、TikTokだけで繋がっているなどが最初から当たり前だったので、そもそも、どの自分をメインとするかという感覚はありませんでした。それぞれのコミュニティがあり、繋がり方を任意に分けられる時代になったということだと思います。
鹿毛
なるほど。そんな風にさまざまな人格を使い分けるZ世代ですから、彼らを相手にビジネスを行う場合も、もはやn=1で見られないということを忘れてはいけないですね。たとえばプライベートの文脈でつながった人にビジネスの話を持って行っても失敗するということになる。
瀧﨑
やっぱり1人の若者の中に別の人格がいることを前提に、「そもそも働きたいときのこの人はどんな顔なんだろう」と考える必要があるかと思います。
■メッセージに余白をつくり、あえて60点の共感を目指す
今瀧
同世代で話していると、Z世代が作ったクリエイティブか、そうじゃない人たちが作ったクリエイティブかは、なぜか明確にわかります。たとえば海外にある日本食レストランで、本当に日本人がやっているか、日本人がやっているように見せているだけか、結構はっきりとわかりますよね。Z世代向けも同じで、Z世代がつくったかそうじゃないかは割と明白ですし、上の世代から"若者用"みたいな言い方をされると、なんだかお子様ランチを与えられているような気分になる。上から目線が透けて見えてしまうと、若者としては抵抗感を覚える部分はあると思います。

また、これまでのマーケティングだと、機能で推すとかマス向けに推すような手法になると思いますが、価値観が多様化している世代にはあまり効きません。なので、共通項としての60点ぐらいの共感を取りに行く。70点だと少し寄り過ぎなので、60点にして、自己自己解釈の余白を残しておくんです。
定
「介在価値」を感じられるかどうかがすごく大事なんですよね。自分が関わったことで結果がこうなった、というのを実感できるのが楽しいんですよね。
鹿毛
今瀧さんが展開している「エモマーケティング」についても少し詳しくご紹介ください。
今瀧
60点のコミュニケーション事例として実際のCMを見ていただくと、できるだけ余白を持たせているのがわかると思います。この情報飽和社会の中でいかにちょっと興味を持ってもらったり、共感してもらえるのかが非常に重要です。それだけで完結させるのではなく、自分だったらどうだろう...と自分に置き換えてもらえるようなクリエイティブにする必要があるかと思います。
たとえば商品名までガッツリ言ってしまうと、そこでもう調べる気が起きなくなってしまう。広告は流し見しているものなので、そこの余白でいかに興味を引くかが大事です。60点の共感のラインを越えて、90点まで持って行ってもいいですが、それだと刺さらない人が出てきてしまう。バランスが求められます。
定
自分で見たことや聞いたことしか信用できない、と言っているZ世代の方もいました。「こうだよ」と教えられたことではなく、自分で「こうだな」と思ったことを信じたいという心理がありそうです。
鹿毛
無茶ぶりになりますが、今瀧さん、Z世代向けの企画をやる上での3カ条を教えていただけますか。

今瀧
そうですね。1つは、インサイトをちゃんと理解すること。やはり"〇〇っぽい"ものになってしまうと、結局誰にも刺さらなくなってしまいます。2つ目は、SNSをきちんと活用すること。ただ、採用とかでとりあえずインスタグラムやTikTokを使ってみたものの、Z世代の当人たちにとっては的外れで白けてしまうといったこともあるので、Z世代の声をちゃんと取り入れることが重要だと思います。3つ目は「エモ」です。エモは、経験×ハッピー×コミュニケーションと解釈しています。伝える媒体はYouTubeだったりテレビだったりバラバラですが、それでも人と人とのコミュニケーションは変わりません。一方通行で伝えるのではなくて、伝えられた人が第三者にどう伝えるかを設計して、企画なりサービスを作っていくべきかと思います。
■競争ではなく、仲間と共に高め合える環境を求めるZ世代
最後に、我々はZ世代にどう向き合うべきなのか、一言ずついただけますか。

瀧﨑
一人の中にあるたくさんの人格を企業が認める、そして仲間になることが大事かと思います。ある大学生の方が「自分が新しいコミュニティで新しい人格と出会ったことで、『こんなことが好きな自分がいるんだ』と気づくことができ、人生が幸せになりました」と言っていました。企業がそこに向き合うことで、彼らの好きなもの、新しい価値感を目覚めさせてあげるような手伝いができたらいいのかなと思います。
定
Z世代はすごく今を大事にしてる世代だと思うので、今はどういう気分なのかとか、どういう自分なのか、ということをしっかりと感じ取りながら対話をしていくと、いいものが生まれるのではないかと思います。
今瀧
若者像の本質的なところは変わらず、時代背景が大きく影響していると思っています。SNSの普及もそうだし、教育の中でも競争を避け、勝ち負けではなくより楽しい方を選ぶといった側面が強かった。それが色濃く出ているのだと思います。なので、"お子様"として見るのではなく、少し背伸びをさせてあげたり、巻き込んであげるようなアプローチをしていくのがいいんじゃないかなと思います。
鹿毛
ありがとうございます。
今日の話で、Z世代像の取っ掛かりだけでも掴んでいただけたら嬉しいです。どうもありがとうございました!

鹿毛 康司
かげこうじ事務所代表
マーケター/クリエイティブディレクター
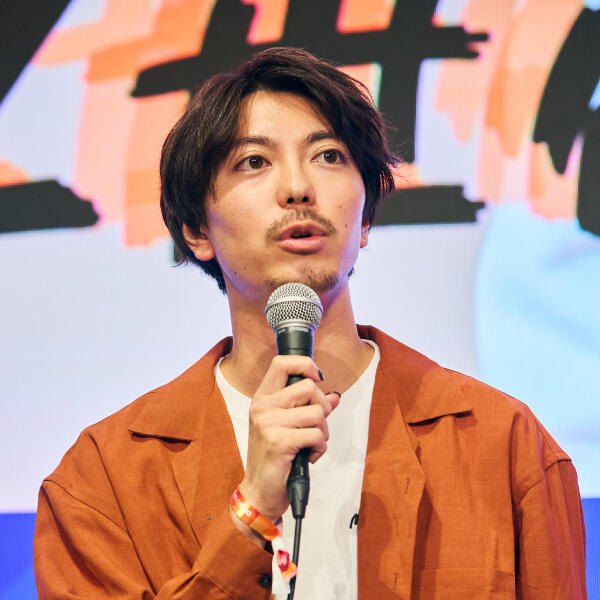
今瀧 健登
僕と私と株式会社
代表取締役

定 絵里加
株式会社学情
経営企画部 マネージャー 兼 インキュベーション室 室長

瀧﨑 絵里香
株式会社博報堂
研究デザインセンター 上席研究員