デジタル化が進み、物質的な豊かさが飽和する現代において、人々の価値観は大きく変化しています。心の充足や精神的な豊かさを求める声が高まる中で注目を集めているのが「SBNR(Spiritual but not religious:宗教的ではないがスピリチュアル)」という概念です。このSBNR層の広がりの実態と、マーケティングや経営への応用可能性について論じた書籍『SBNRエコノミー「心の豊かさ」の探求から生まれる新たなマーケット』が3月に発刊されました。出版を機に、著者の一人である博報堂のマーケティングプラニングディレクター 宮島達則と、日本香堂ホールディングスの小仲正克社長との対談が実現。日本、そして世界でSBNR層を魅了する"香りの力"について語り合いました。

海外へ渡る「線香」「お香」
香りが開く新たな市場
宮島 小仲社長は、私たちが2023年に発表した「SBNRレポート」(博報堂+SIGNING)をご覧になり、SBNRに深い関心をお寄せいただきました。それをきっかけに、私も日本香堂さんのお仕事に関わらせていただくようになりました。改めて、当時SBNRのどんな点に着目されたのか、教えていただけますか。
小仲 物質的に豊かな生活を送ることこそ幸福だとされていた時代から、最近は「ウェルビーイング」と言われるように心の充足感が重視されるようになっています。そこにSBNRの概念がうまく紐づくように感じ、事業のヒントになるのではと思ったのです。今回書籍も読ませていただいて、SBNR層の4つのタイプ分類など、自分自身が日頃考えていたことを、上手く整理してもらっていると感じました。

『SBNRエコノミー』より (c)Getty Images
宮島 ありがとうございます。日本香堂さんといえばお線香やお香ですが、こうした商品は、人とのつながりを重んじたり、心を整える時間を大切にするSBNR層とも非常に親和性が高いですよね。
小仲 香りには香りそのものの価値ももちろんありますが、そこから想起される記憶や想像、インスピレーションといった、情緒的なものに伴う価値が大きいと思っています。これはまさに、SBNRの要素が多分にあるととらえています。
宮島 なるほど。近年では海外のラグジュアリーブランドとのコラボやOEMも増えているとも伺っています。海外マーケットでの広がりには、どんな手応えを感じていらっしゃいますか?
小仲 海外でのインセンス(お香)カテゴリーの売上が増えています。先日、フランスの香水学者にインタビューする機会があったのですが、歴史的に見て、香水業界には3つのイノベーションがあると語っていました。「精油技術の確立」「合成香料の進化」「マーケティング」、そして次のイノベーションは「スピリチュアリティ」ではないかと。
「これまで香水というのは、官能性など他人を魅了することが目的だった。しかしこれからは自分のために使うものになる」という話が印象的でした。ラグジュアリーブランドとお香メーカーの協業など、かつては考えられなかったことですが、日本の香りに禅的なスピリチュアルの要素を強く感じているのだと思います。
宮島 海外市場では、具体的にどんなブランドが人気なのですか?
小仲 ロングセラーの「毎日香」(海外名モーニングスター)は、もともとアメリカのヒッピームーブメントの中でドラッグの匂い消しとして使われはじめた商品です。いまではインセンスの代名詞に近い存在となり、日常使いの商品として定着しています。こうした背景から、年齢層はやや高めです。

一方で、近年では、マインドフルネスのブームの後押しもあり、メディテーション(瞑想)用途のインセンス(お香)の売り上げがグローバルに伸びています。サンダルウッド(白檀)のようなオーセンティックな香りも好まれますし、合成香料を使わないナチュラルな素材を求める層もいます。香料を一切使わない、自然のものだけを使った「CHIE MEDITATION」は、特にヨーロッパで人気です。YZ世代を意識した色づかいのパッケージの「SCENTSUAL」などの商品もあります。


香りの「型」と「道」に見る、日本人の体験設計力
宮島 日本古来の伝統芸道の一つに、「香道」がありますよね。香道では、香木を焚いて、香りを「聞く」(嗅覚だけでなく全身で香りを感じることを意味する言葉)ことや、香りの違いを当てる「組香」といった遊びをする「香席」という場がある。先日、日本香堂さんの450年記念の香席に参加させていただいたのですが、とても素晴らしい体験でした。
小仲 私どもは2018年、フランスにNPO法人のKodo Associationを設立しています。香席を開くと、参加してくださるフランス人はみなさん驚くほど関心が高い。日本での香席とは全く雰囲気が違っていて、とにかく質問が多いんです。香道と禅の関係や、香道の香りのこと、和歌に対する質問など、自分の仮説を持ってこられる方がたくさんいます。集う人も文化的な知識層や、ウイスキーやシャンパンのような嗜好品に関わる方、アーティストなどもいらっしゃいます。

宮島 文化的に感度の高い方々が日本の香道に関心を持たれているのですね。本書ではSBNRの考え方を活かすアプローチとして、「道化(みちか:その行いを極めながら、自己を探求すること」「型化(かたか:既存の行動に新たな形式やルールを取り入れ、あえてその型にはまること)」「聖地化(特定の場所や空間に、精神的価値を付与すること)」の3つを提案しています。香道も「道」のひとつですが、まさにこういった設計とのつながりを感じます。
小仲 特に「道化」と「型化」の設計力については、日本人は秀でていると思います。「型」があるから「道」が生まれ、この2つは密接に結びついている。
香道は、「六国五味」(香りを表現する分類法)と「組香」(香り当ての遊び)という「型」があります。それを極めていくことで「道」になる。さらに、香道発祥の地である銀閣寺という「聖地」もある。そう考えると、香道はまさに「道化」「型化」「聖地化」によって成り立っている好例です。「型」があるからこそ、時代の文脈に合わせて「崩し」(香道における自由な表現や革新的な試み)もできる。ワインやウイスキー、日本酒でも応用できる可能性がありますよね。

宮島 私も香席を実際に体験することで、本当に体験設計がよくできていると感じました。初心者でも、香りを当てるというゲーム性から入りやすく、集中すると微細な香りの違いが分かり、五感全体で体験する中で、いつの間にか香りの世界に深く入り込んでいる。香りの素人だった自分が、短時間で微細な変化に魅せられる体験をしました。この体験設計力は、長年文化が成熟する中で純化されたものだろうと思いますし、おっしゃる通り他の分野への応用も可能だと感じました。

小仲 香道は「お客様が主役」であることも特徴です。誰が出香したかなども記録され、香りを当てた人にはその記録を記した奉書をお渡しします。一期一会で二度と同じメンバーは集まらない、その場を共有する寄り合いの楽しさもあります。
宮島 しかも言語を介さない五感のコミュニケーションですから、言葉が違う国の人同士でも一緒に楽しむことができますよね。
SBNRと香りの市場の可能性
内省から自己実現へ
小仲 今年、日本香堂グループ450年のプロジェクトとして「450プロジェクト"聞く〜awake your spirit〜"」を立ち上げました。香道の「聞く」という言葉には、単なる嗅覚だけでなく、五感を使って香りと向き合うことで感性を、深く研ぎ澄ませていくような感覚が含まれています。そのような「香りとともに旅をする時間」を提供していくという考えで、1年間かけて過去・現在・未来の3つの視点から、新事業やプロジェクト、新製品を発表していきます。
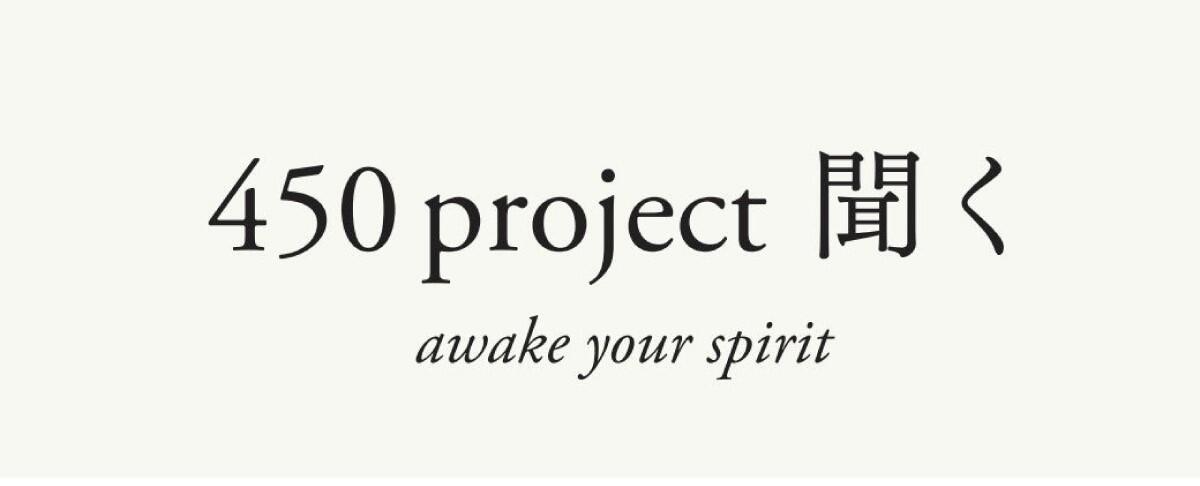
具体的には、書籍や新作のお香の発売、そして同業種の松栄堂、鳩居堂、そして無印商品とのコラボイベントなどによって、一人でも多くの方に香文化を知っていただく機会にしようと取り組んでいます。香りと共に過去から未来、そして異郷の地や故郷、そして心の中を旅していただきたいという思いを込めて、グループの新スローガン「香りと旅する」と設定し、CIも刷新しました。このスローガン自体に、内省や自然とのつながりを重視し、長期思考を志向するSBNRの要素が多分に含まれているとも言えますね。
宮島 香りの価値を「自分と向き合う時間を生み出すもの」と再解釈しており、SBNR層とまさに親和性が高いと感じます。海外の方々も含めて、この価値を広めていくのだと思うのですが、日本と海外では、SBNR層へのアプローチに違いがあると感じますか?
小仲 興味深い違いがあると思います。日本では、スピリチュアルや精神性というと、どちらかというと心のやすらぎや癒やし、つまりマイナスをゼロに戻すような感覚が強い。「整える」といったニュアンスですね。一方、海外、特にマインドフルネスなどに熱心な層を見ていると、「なりたい自分に近づいていく」といった、ゼロをプラスにしていく、すごくポジティブな文脈を感じます。そこから「パワー」を得るような感覚ですね。
宮島 パワーという視点は重要ですね。SBNRを癒やし効果だけで捉えるのではなく、具体的な効果効能や機能性を伴って伝えていくことが、特に海外市場においては重要になりそうです。科学的なエビデンスに基づいたマーケティングも必要になってくるでしょう。
小仲 まさに海外でお香を広げていく上では、ストーリーとエビデンス、この二つが揃うことが重要だと感じます。日本と比べて効果や実感を重視する傾向が強いですから。
宮島 ストーリーについて言えば、私自身、香席を体験して一つひとつの香りの違いを知ることで、「良い香り」に対する納得感が一段引き上げられました。同じように、例えばロングセラー「毎日香」についても、その香りである白檀はどんなストーリーを持っているのか、なぜ神聖な木と言われるのかを伝えることで、単なる「いい香り」から一歩進んで、そのストーリーを感じながら生活の中に取り入れてもらえるようになると思います。また白檀がもつ清らかなイメージをもっと拡張していければ、供養で使うお線香以外のシーンにもブランド価値を拡張できるのではないかと考えています。書籍の中にある「シン消費」(心の平安・充足・自己成長や自分の信じられるものにお金を使う)というのが、まさにそれに当たります。
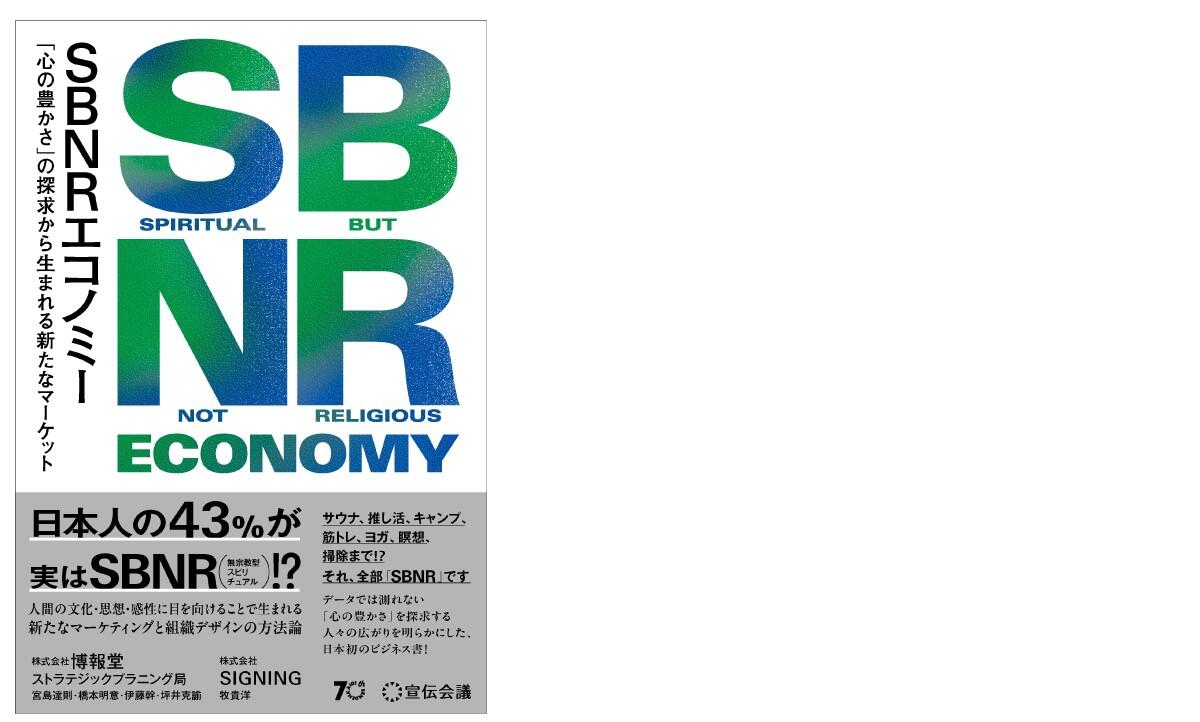
『SBNRエコノミー「心の豊かさ」の探求から生まれる新たなマーケット』
小仲 我々メーカーは、原料のストックや香りを生み出すノウハウの蓄積には強みがあるのですが、こうした情緒的なアプローチはまだまだ弱いところがあります。
宮島 これまでおっしゃられていたように、香りを自分と向き合い、内省し、成長していくためのツールとなり得るものとして発信する。そして、そのストーリーや背景にある歴史、そして科学的なエビデンスといった付加価値まで含めて受け取っていただけるようになると、単なるモノ消費、コト消費を超えた「シン消費」としてのビジネスチャンスが生まれるのではないでしょうか。
小仲 香木のように長い年月をかけて完成されるものには、それ自体にパワーや神聖さといったストーリーが宿っています。そのストーリー性、情緒的な価値、余韻感などがシン消費的な要素と関わってくると、その価値は長く続いていきそうですね。
宮島 日本でも、若い世代、特にZ世代は自己肯定感が低いといった社会背景もあり、内省や自己実現への関心が高まっています。彼らにとって、自宅で使う香りはまさにパーソナルな空間を作り、自分と向き合うための重要なアイテムとなり得ます。フレグランス市場の中でも、お香は特に内省的なアイテムとして、若い世代に響く可能性を秘めていると思います。


小仲正克(こなか・まさよし)
日本香堂ホールディングス 代表取締役社長
1967年生まれ。立教大学卒。1990年三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行。1995年日本香堂入社。研究室、R&D事業部所属。以後、取締役 新市場開発本部長、常務取締役を経て、2000年に代表取締役社長に就任。2011年日本香堂ホールディングス専務取締役、2015年より現職。趣味は水泳、テニス、読書、音楽鑑賞。

宮島達則(みやじま・たつのり)
博報堂 マーケティングプラニングディレクター
2019年博報堂入社。入社以来、食品/飲料/日用品/通信など多岐にわたるカテゴリーのマーケティング・ブランディング戦略立案に従事。一見、非合理的な生活者心理にロジックを見出し、言語化するプラニングを得意とする。また僧侶としてのバックグラウンドを活かし、寺院のブランディングや線香のマーケティング等の経験も。
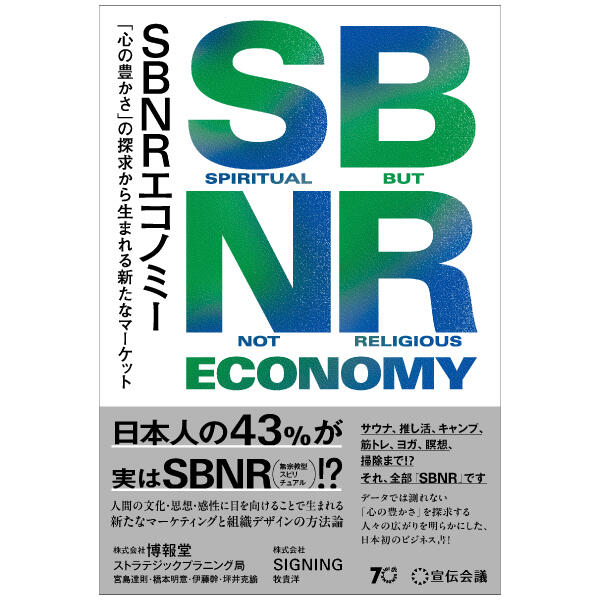
『SBNRエコノミー「心の豊かさ」の探求から生まれる新たなマーケット』
株式会社博報堂ストラテジックプラニング局、株式会社SIGNING著/定価:2,200円
SBNR層の拡大に注目し、精神的な豊かさや幸せを求める同層の拡大の理由、そしてビジネスへの応用可能性を論じる日本初の書籍です。日本人は43%がSBNRに該当すると言われ、その価値観を理解することはマーケティングや経営にも有効です。本書では、彼らの価値観やライフスタイルを分析するとともに、マーケティング・組織デザインにSBNRの考え方を応用していく具体的な方法を提案します。
※「AdverTimes.(アドタイ)」に2025年5月28日に掲載された記事から抜粋したものです。