
東京・汐留にあるアドミュージアム東京にて、2024年4月27日~8月31日、企画展「コレって広告?!展 ~拡張する21世紀の広告クリエイティブ~」が開催されました。同ミュージアムからの声掛けで、博報堂クリエイティブディレクターの須田和博が企画と監修を務めました。
21世紀に入り、広告を取り巻く環境は激変しています。インターネットの普及とスマートフォンの登場、またSNSの台頭などにより生活者や社会が変容し、広告の手法だけでなくメッセージの考え方にも影響を与えています。須田はそうした21世紀の広告を俯瞰し、「生活者の視点では『これも広告だったの?』と驚くような事例が次々と登場している」ことに注目。これを本展の全体コンセプトとし、複数の「拡張」をひも解きました。
本記事では企画展アーカイブとして、約200の展示広告から代表的なものを交えながら、全体を解説します。
監修:須田和博(博報堂)
アートディレクション:細川剛(博報堂)
デザイン:MILK、宮崎琢也(TBWA\HAKUHODO)
CG:汪駸
年表編集:高田豊造(コーダ工房)
年表デザイン:KARAPPO Inc.
協力:(株)博報堂/(株)博展
主催:(公財)吉田秀雄記念事業財団
ライブラリー選書:B&B
顧客の近くに行こうとしたアイデアを集める
ここアドミュージアム東京は、常設展として、江戸時代から現代までのさまざまな広告を紹介しています。今回の企画は、その常設展からつながるような21世紀をテーマとした企画展を開催したい、というところが発端でした。まとめ方は任せていただいたので、それなら「若い人が"これって広告だったんだ!"と感じるものを集められたら」と考えました。
これは広告なんだろうか? と疑問に感じるような事例が、近年いくつも出てきています。以前は"広告"とは扱われなかったかもしれないけれど、ちゃんと広告としての役目を果たしている。そして"広告"と思われないことで、ユーザーや生活者に近づいて、メッセージを伝えたり、問いを投げかけたりするようになっています。

広告が本来いなかったはずの場所にも入って、顧客の近くに行こうとする。その意志が具現化したのが、本展でゾーン分けした複数の「拡張」です。21世紀の広告には、そうした意図が顕著にみられます。
本ミュージアムの常設展の後半に展示されている20世紀末の広告は、新聞広告やテレビCMなどが中心で、いわゆる「枠」のあるマスメディアの爆発的な成長がわかります。それが21世紀になってインターネットが浸透し、スマホが当たり前になって、「枠」が溶けていきました。メディアとテクノロジーの進化に伴い、広告クリエイティブが既存の広告の姿からさまざまに拡張して成長しているのが、21世紀の広告の特徴です。
結果として、ユーザー側から見ると「えっ、これも広告だったの?!」と思うような広告が多く登場しています。そんな驚きや発見を今回の展示の拠り所にしたいと考えて、全体の軸としました。
4つの「拡張」と、その源流を探る
広告が"広告然"としなくなっている、というのは、実は自分の中で長年のテーマでした。ACC(全日本シーエム放送連盟)の「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」に10年ほどインタラクティブ部門があった時期、2016-17年に審査委員長を務めたのですが、16年に設定したテーマが「ソレって広告なの?」でした。本企画展を準備して、この傾向はますます強くなっていると実感しました。

全体は、4つの「拡張」ゾーンと、「拡張の源流」として広告コピーの変遷を追う年表、そして広告業界の方々のコメントとともに、来場した皆さんに「広告って何ですか?」を書いてもらう参加型コーナーの全6ブロックで構成しました。
4つの拡張はそれぞれ、「リアルの拡張」「メディアの拡張」「発信者の拡張」「価値観の拡張」です。これらは年代がきっちり分かれているわけではなく、互いに絡み合っていますが、ゆるやかに構成しています。
まず、マスメディアの枠からリアルな世界に広告がはみ出していき、次にガラケー(※「ガラパゴスケータイ」と呼ばれる、スマートフォン普及以前に日本で独自の進化を遂げた携帯電話)やスマホが生活者に浸透したことで、メディアが広がりました。
並行してSNSが普及すると、皆さんも体感されているように、ごく一般の方々も発信者になりました。テキストや動画などのクリエイションに留まらず、いろいろな意見が世の中に投じられるようになり、それに企業も影響を受けた結果、広告が価値観の発信にまで拡張していきました。生活者の多様な価値観を認める姿勢や、あるいは「もっと主張していい」と促すような広告が、ここ5年ほどで広がってきています。
そんな4つの拡張と、そのときどきの時代や生活者の気持ちを捉えた企業メッセージの変遷について、代表的な広告とともに解説したいと思います。
ゾーン1:リアルの拡張~パブリックをハックする~
第1ゾーン「リアルの拡張」では、従来の媒体スペースから、実際の街や実空間にはみ出していった広告を集めました。21世紀になって、まず「媒体という枠から拡張した」流れがありました。ここでは大きく、①媒体枠をベースにその可能性を広げようとしたものと、②媒体ではなかったものや場所を媒体化しようとしたものに分けることができます。

かつての銀座ソニービルの懸垂幕メディアを利用した、ヤフー防災広告 「ちょうどこの高さ。」(ヤフー/2017)は、①の代表的な事例です。媒体自体は以前からありましたが、実際の地面からの高さを「東日本大震災の津波の高さ」として示して、見る人をハッとさせました。「バーティカルフットボール」(アディダス/2003)も、従来の屋外広告の枠で、ビルの上から人とボールを吊るして実際にサッカーをするという斬新な使い方をしています。
Mr.Children『ITʼS A WONDERFUL WORLD』 中吊り「レース」(トイズファクトリー/2002)は、見慣れた電車の中吊りも「こんなふうに使えるんだ」と、目を引く広告でした。
一方、②の媒体ではないものや場所の活用では、ペットボトルのキャップを使ったペプシコーラ「PEPSI BOTTLE CAP COLLECTION」(サントリー/1998〜)が象徴的です。当時を知る方々は、このキャップを目的に"大人買い"現象が起きたことを覚えておられるでしょう。分類するならノベルティやおまけになりますが、その能力を限界まで高めています。

ただ広告として消費されるのではなく、顧客の暮らしのそばに置いてもらえるもの、かつ、物販の促進という広告機能のど真ん中を担い切っていると思います。パッケージの拡張としても生活文化としても、重要な事例です。
また、このゾーンに王道のテレビCMである「Dear WOMAN」 資生堂『TSUBAKI』CMメッセージソング TSUBAKI「春・宣言」(資生堂/2006)を配置しています。SMAPの楽曲とタイアップした大型出稿ですが、私が注目したのは、街なかの映像媒体で大量に流れたことで、街という空間に広告が拡張していった点です。クリエイターが広告枠の外に視野を広げた結果、新しい広告の展開が生まれたように思います。
ちなみに、ペプシコーラもTSUBAKIの事例も、敬愛するアートディレクターの大貫卓也さんが手がけたものです。ゾーン1で紹介した他の事例も、クリエイターが広告主の意図を汲みながら、既存の広告枠や使い方のセオリーを打ち破ろうとした軌跡だと感じます。
ゾーン2:メディアの拡張 ~テクノロジーが生活の一部に~
2000年~2010年ごろ、広告がリアルに拡張しながら、世の中にはインターネットとデジタル媒体が急速に普及していきました。いわゆる"ネット広告"の黎明期、そして個々人が持ち歩くメディアであるガラケーやスマホが広がった時期の事例を、メディアの拡張としてゾーン2に集めています。それらと同時に広がった、各種SNSのロゴやグッズも紹介しました。

21世紀の広告はすべてそうとも言えますが、特にこのゾーンの事例は、時代背景的にテクノロジーの進化と密接です。
ネット広告が登場して何が変わったかというと、生活者にとって広告が「見聞きする」だけでなく「使う」ものになったことだと考えています。自分にとって使う価値があるものを、進んで受け入れていく。企業からすると「使ってもらえる」広告という概念が生まれたのがこの時期です。そして使われるものはネットの世界でどんどん広められていく、これは顕著な変化です。

その代表が、PC上に配置する時計アプリ「UNIQLOCK(ユニクロック)」(ユニクロ/2007)です。時刻表示と、ユニクロのウェアを着たダンサーが音楽に乗せて踊り続ける映像が組み合わされ、ずっと見ていられるような気持ちよさで数多くのユーザーに使われました。私が担当した、泣きやみ動画 「ふかふかかふかのうた」(ロッテ/2012)も、「赤ちゃんが泣き止む」と親御さんの口コミで広がっていきました。
ほかにも、クリックするとブラウザ全体をジャックする体験型の広告や、ネットの仕掛けを使った目新しい広告など、黎明期ならではの形がおもしろがられていました。ネット広告に慣れた現代の生活者には、同じものは通用しないでしょうが、使うことで広がる流れは健在です。たとえば、サンリオのキャラクターをカスタマイズしてつくれる「ちゃんりおメーカー」(サンリオエンターテインメント/2015)などは、その系譜でしょう。
一気にアナログになりますが、「使ってもらえる」点でもうひとつ挙げたいのは、携帯電話のストラップです。これもメディアのひとつであり、とても日本的で不思議な現象でした。もともとは落下防止のために手首に掛けるものでしたが、すぐに紐よりチャームがメインになり、飲料や生活雑貨など、さまざまなブランドがノベルティや商品として世に送り出しました。

当然、そのブランドが好きだから付けるわけで、付けているともっと好きになる、"ブランドラブ"が増大する好循環が生まれていました。ただ、iPhoneにはストラップの穴がないので、iPhoneをはじめスマホがガラケーに代替する過程で、残念ながらこの文化が廃れていきました。
また、ここで展示していた昔のガラケーは触ることができ、とても人気で皆さん手に取られていました。今、私たちはスマホを横にして映像を楽しんでいますが、ガラケーの後期には、縦の画面を物理的に横に90°回転できる機種がありました。この発想は、ものづくりの日本メーカーらしいと思います。

※後編へ続く
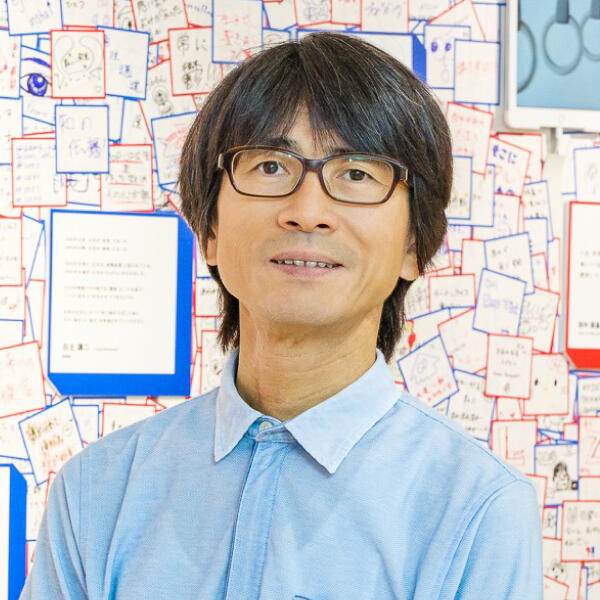
須田 和博
博報堂 クリエイティブディレクター / UNIVERSITY of CREATIVITY ディレクター / スダラボ エグゼクティブ・クリエイティブディレクター
1967年新潟生まれ。1990年多摩美大卒、博報堂入社。AD、CMプラナーを経て、インタラクティブ領域へ。2009年「ミクシィ年賀状」TIAAグランプリ。2014年スダラボ発足、「ライスコード」でアドフェスト・グランプリ、カンヌ・ゴールドなど、国内外で60以上の広告賞を受賞。2016〜17年 ACC賞インタラクティブ部門・審査委員長。2019年「MRミュージアム」日本イベント大賞グランプリ。2023年より多摩美術大学・非常勤講師、および内閣府SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)ピアレビュー委員。著書「使ってもらえる広告」
https://uoc.world/people/details/?id=gy0dm90rbb2x