新規事業を生む企業や組織は何が違うのか。1960年の創業以来これまで多くの新規事業を世に生み出してきたリクルートに、その秘訣を伺います。第二回は、リクルートのRing事務局長である渋谷昭範氏をお迎えし、事業を生む会社の人と仕組みをテーマに、経営層、マネージャー、担当者のマインドセットや行動のヒントについて、博報堂ミライの事業室の吉澤到室長、鈴木貴博と議論していきます。
第一回「新規事業を生む組織の創り方―リクルート×ミライの事業室スペシャルセッションVOL1」はこちら→ https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/topics/2023/06/4272.html

■人にフォーカスをあて、新しい価値をつくっていく
鈴木
今回のゲストは、リクルートで40年続く新規事業提案制度Ring の責任者であり、新規事業開発室の組織長でもある渋谷さんです。まずは渋谷さんにずばりうかがいます。リクルートがこれほどまで新規事業に熱量高く取り組むのは、つまるところどうしてなのでしょうか?
渋谷
経営理念の実現、企業文化の継承、そして変化対応力の体現という3つの理由があります。リクルートの始まりは大学新聞の求人広告で、そこから住宅、旅行、結婚などへと領域を拡大していきました。(詳細はvol1記事参照)そして時代の変化にあわせて、紙からネット・アプリ、SaaS事業などビジネスモデルチェンジを繰り返してきています。だからこそ、リクルートにとって新規事業を創り続けるのは日常でありますし、特許や工場など目に見える資産を持たないので、人の力で新しい価値を生み続けるしかなかったのです。だから「どうしてなのか?」と聞かれると「リクルートだからです」という答えになります。

吉澤
そもそもの会社の成り立ちからして、新規事業との関わりが深かったのですね。
渋谷
そうです。創業の原点がそうだったということもあり、いまも新しいことに挑戦する文化があります。その企業文化とは「1.起業家精神 2.圧倒的な当事者意識 3.個の可能性に期待し合う場」と定義していて、まさにRingはこれらを体現する制度といえます。
吉澤
新規事業提案制度は今でこそ多くの大企業が取り入れていますが、リクルートさんのRingはその先駆けでしたね。どのような制度なのでしょうか?
渋谷
Ringは1982年に始まった事業提案制度で、誰でも起案できます。現在も続くいくつもの事業がRingから生まれました。毎年開催され、4月~6月に約1000件のエントリーがあり、数回の審査を経て、翌年2月にグランプリを決めます。そこから事業開発に進めるのは5、6件ほどです。若い世代中心に非常に熱心に取り組んでいます。1年間サイクルで社員に「そろそろRing応募の季節か」と感じてもらい、企業文化としての定着を狙っています。
■なぜRingのようなボトムアップの提案制度を続けているのか?

渋谷
手間も時間もかかるこうしたやり方を続けている背景には、アイデアには多様性・量が重要なこと、一次情報に触れているアンテナの高い社員を活かしたい、といった理由があります。
リクルートでは、事業開発を「発見」「組み立て」の2つの段階に分けて考えています。「発見」段階においては、アイデアのソーシングに絶対量が必要だし、観点や切り口の多様性や一次情報が不可欠で、個人のアンテナの高さも必要。一方「組み立て」段階では、一定の知識やスキル、不確実でも進む推進力や既存事業と異なる思考、経験者が必要です。この「発見」をRingというスキームでたくさん集め、厳選した数件を新規事業開発室で伴走しながら進めるのです。
鈴木
仕組みを整備して多数の提案を募っても、その中でメガヒットと呼べるような新規事業へと羽ばたくようなものはそう簡単にはつくれない、というのが一般論としてあると思います。それを頭ではわかっているつもりでも、実際に自分が当事者となったときになかなかヒットを出せないと焦ったり落ち込んだりしませんか。
渋谷
本当に簡単ではないですね。私がシリコンバレー赴任時に実感したのが、あのエリアに世界中から人もアイデアも大量に集まるからこそ何かが生まれるということです。そこに原点があります。
ワインに例えると、いいワインづくりには気候、風土、栽培・醸造法の全部が大事ですが、そのなかでも金賞を獲るワインはなかなか生まれません。ただ、気候はコントロールできなくとも、風土は年月をかけて育てられるし、栽培法は最新のメソッドを取り入れていけばいい。実りの悪い年でも、落ちた実が肥料になって次の年につながる。少なくとも5年10年やるべきで、うまくいかないところはチューニングしながらようやく当たり年が出てくるということだと思います。だから、まずは風土をつくるために、やり続けることが重要だと思います。
吉澤
私自身も新規事業は農業に近いのではないかと考えることがあります。どんなに環境を整えたとしても、考えたようにはいかない。忍耐力も必要ですし、最後は天に任せるというか「どうにか育ってください」と祈るしかない(笑)
渋谷
その通りです。新規事業は数年で大きな事業が生まれなくても仕方がありません。その数年間を経て、ようやく金賞級のワインをつくれる土台が整ってきたタイミングかもしれません。1・2年だけやって止めてしまうのは一番もったいないですね。

■上位にあるのが企業カルチャーだから、徹底できる
鈴木
一般的に、新規事業部門は現業部門からネガティブな視線を向けられてしまうことも少なくないと思います。リクルートではなにか対策していますか?
渋谷
よく聞かれるポイントです。いくら経営層が新規事業の旗振りをしていても、現場の上司が「そんなことより現業の目標達成を優先すべきだよね?」などと言ってしまうとどの社員も活動できなくなってしまいます。
吉澤
現業の上司からそう言われてしまうと、社員は動けなくなってしまいますね。
渋谷
そこでリクルートでは、新規事業提案者がオフィシャルに応援される仕掛けを導入しています。Ringでは一次審査を通過すると、所属部署の上長の応援コメントを先に集め、顔写真つきで公開します。そうなると、どの上長もネガティブなことは書けず応援コメントを出してくれます。それを読んだ社員は、周りの皆から応援されているんだと感じるでしょうし、他社員からも応援メッセージが数多く集まり、オフィシャルに応援する文化が醸成されます。
吉澤
さすが40年続いている仕組みだけあって、細部にわたって工夫がなされていますね。特に感心するのが、提案者だけが奮闘するのではなく、周囲の方々も多大な手間をつぎ込んでいる点です。全社が一丸となって新規事業をつくっていくのだという企業文化が、Ringという制度を通じて組織全体に浸透しているのですね。

■何か匂う、その裏にある手触り感こそ大切
鈴木
新規事業の選定基準はどのように設定されているのですか。
渋谷
提供価値、市場性、事業性、優位性の4つですが、これらは基準ではなく、あくまでも観点です。数値的なことは厳密には求めないし、試験のように何点以上ならクリアといった見方もしません。未来のことなんて誰もわからないので「何か匂う」「もっと話を聞いてみたい」で判断するのが妥当だと思っています。ただし、1人の主観ではなく複数人の主観で評価することで公平性を担保しています。3人以上が見て、1人でもイエスが付けば通過候補としてプールされて選定会議で議論されます。全員がいいと思うものは、誰かがすでにやっていることだったりしますから、1人がイエスでほかの2人がノーを出したものの方が面白いケースがありますね。
鈴木
意外です。事業計画の精度はそこまで求められないということですか。
渋谷
Ringへの提案時点では事業計画は提出してもらっていません。通過してから詳しい人間がサポートして精緻に計算するので、何に一番コストがかかりそうかのアタリを書いてもらうだけで十分です。市場規模の試算も同じですが、書類審査では、ちゃんと考えて起案を書いているかに注目しています。とはいえ一番大事なのはやはり提供価値で、誰も気づいていない切り口で顧客を見て、「実はこんなことになっているんですよ」という視点が一番大切。
鈴木
Ringという仕組みを回すことで、膨大なアイデアを現場の社員が提案し、それがリクルートという会社の風土づくりにつながっている。すごいなと思います。

渋谷
最近は、新事業提案制度に大航海時代のアナロジーを見ています。大航海時代は欧州の視点で香辛料の発見から「インド航路を探す」「交易を拡大する」というテーマ設定がされてスタートします。コロンブスが西インド諸島を見つけた数十年後に「新大陸」と再定義されました。そして、新大陸に多くの人が渡り都市を形成していった歴史です。
鈴木
再定義という概念を導入しているのが興味深いです。再定義した後の活用、つまり新大陸での営みの形成や運用というのがポイントのひとつになりそうです。
渋谷
最初は一人が見つけた小さな兆しから、ちょっとやってみようぜといって、小さく動き出す。そんな小さな挑戦を多くの人が行う。そして、見つかった事実から新しい理解や再定義が行われ、新しい世界や事業構想が見つかる。挑戦する起案者とマネジメント層がこのプロセスを繰り返すことで、大きな価値を創れるんじゃないかなと思っています。
吉澤
どの事業もリアリティがあって構想で終わらない印象です。現場に通いお客さんのことを見ているから、発想の起点自体が現場主義であり顧客起点ですよね。そこが強みだと感じます。
渋谷
類似の表現として、Ringでは「手触り感」という言葉をよく使いますね。先に面白いアイデアを思いついて、ネットで調べただけのようなプランは見透かされます。実際に起きている事実や顧客の本当の声、手触り感のある発見という起点が重要ですね。
同様に「解像度を上げる」という言葉もよく使います。同じように見える顧客でも、どういう条件だとニーズが顕在化するのか?と解像度が上がります。このプロセスを経て、小さな兆しの発見から「リアリティ」や「顧客起点」を磨いていくのが浸透しているんだと思います。

■新規事業の文化を人事制度へも連動させる
吉澤
選考を通過し事業を立ち上げるとなると、人を増やしていくことも必要になってきますよね。それをふまえた柔軟な人事制度があるんですか。
渋谷
まず最初に「ニーズがあるのか?」を検証しますが、この段階では提案者は20%兼務で新規事業開発を担当します。このフェーズを通過できれば、所属組織人事との調整なく100%主務で新規事業開発室に異動して「儲かるのか?」を検証します。「拡大できるか?」のフェーズになると、社内から希望者を募り現業調整なしに異動してきてもらう人事制度を利用することができます。
吉澤
上位にあるのが企業カルチャーだから、徹底できるんでしょうね。同じことをやろうとしても、多くの企業で「現場で稼いでいる人間を引きはがすつもりか」と反発が起きそうな気がします。
鈴木
僕も前職で公募制度の事務局をやっていましたが、既存事業とのコンフリクトや、いまやっている仕事に対して食い合ってしまうことがあり、審査に苦労することがありました。いま何百億稼いでいる現場の邪魔にならずにディスラプティブな案を通すというのは、相当ハードルが高いと感じました。リクルートがRingという制度を社内で完全に回せている背景には、企業文化と、40年という歴史が持つ意味が相当強くあるように思います。

渋谷
その先の未来を描けるならいまの事業をあえて踏み越えていく、という意思決定をした歴史がリクルートにはあります。諸先輩方が創ってこられたリクルートの企業文化なんだと理解しており、将来に継承していきたいと思っています。
吉澤
まさにベンチャー精神が今日のリクルートを創ってきたというわけですね。今日は大変貴重なお話をありがとうございました。

渋谷 昭範
株式会社リクルート
Ring事務局 局長・新規事業開発室 インキュベーション部 部長
大学卒業後の1997年、NTT持株会社の研究所に入社。ベンチャーを経て、2005年にリクルートに入社。WEBマーケを担当後、2010年に上海の現地子会社に赴任。その後、シリコンバレーとインドでベンチャー投資を担当。2014年にソフトバンクに転職し、事業開発を担当。その後、ベンチャー企業1社へ経て、2017年にリクルートに再入社し、買収したベルリンの子会社のCMOとして赴任。2018年に東京に戻り、リクルートの新規事業提案制度「Ring」の企画・運営責任者に就任(現任)。リクルート時代にNew-RINGに入賞、ソフトバンク時代にイノベンチャー最優秀賞を受賞。経営学修士MBA取得
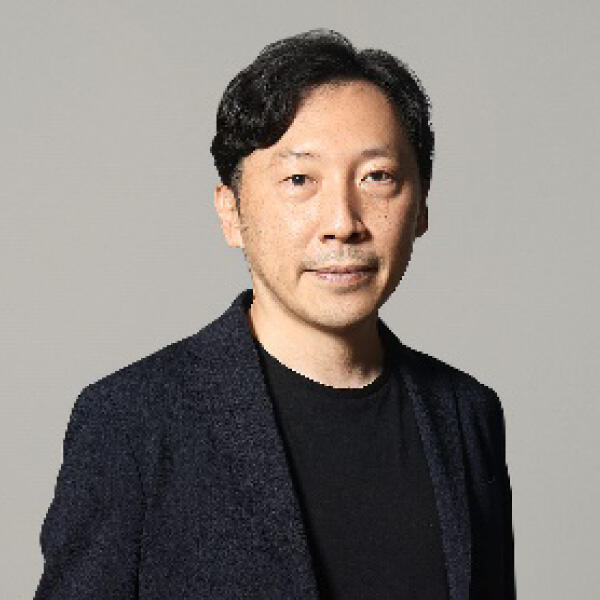
吉澤 到
博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ
ミライの事業室 室長・エグゼクティブクリエイティブディレクター
東京大学文学部卒業。ロンドン・ビジネス・スクール修士(MSc)。1996年博報堂入社。コピーライター、クリエイティブディレクターとして20年以上に渡り国内外の大手企業のマーケティング戦略、ブランディング、ビジョン策定などに従事。その後海外留学、ブランド・イノベーションデザイン局 局長代理を経て、2019年4月、博報堂初の新規事業開発組織「ミライの事業室」室長に就任。クリエイティブグローススタジオ「TEKO」メンバー。Earth hacks株式会社取締役。著書に「イノベーションデザイン~博報堂流、未来の事業のつくり方」(日経BP社)他

鈴木 貴博
博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ
ミライの事業室 第一事業開発グループ ビジネスデザインディレクター
自動車会社新卒入社。 製造、製品設計、製品企画、経営戦略を経験。その後海外大学との新規事業連携や、社内初の事業公募制度設計、立ち上げ後、事務局実務TOPとして運営。全社横断の新規事業に携わり、社内初のMaaSビジネスの企画担当。2018年~19年には兼業として大手メディアサービス会社に外部コンサルタントとして参画。その後、自動運転技術開発会社にてソフトウエアビジネスの新規事業開発を担当。2022年博報堂ミライの事業室に参加。