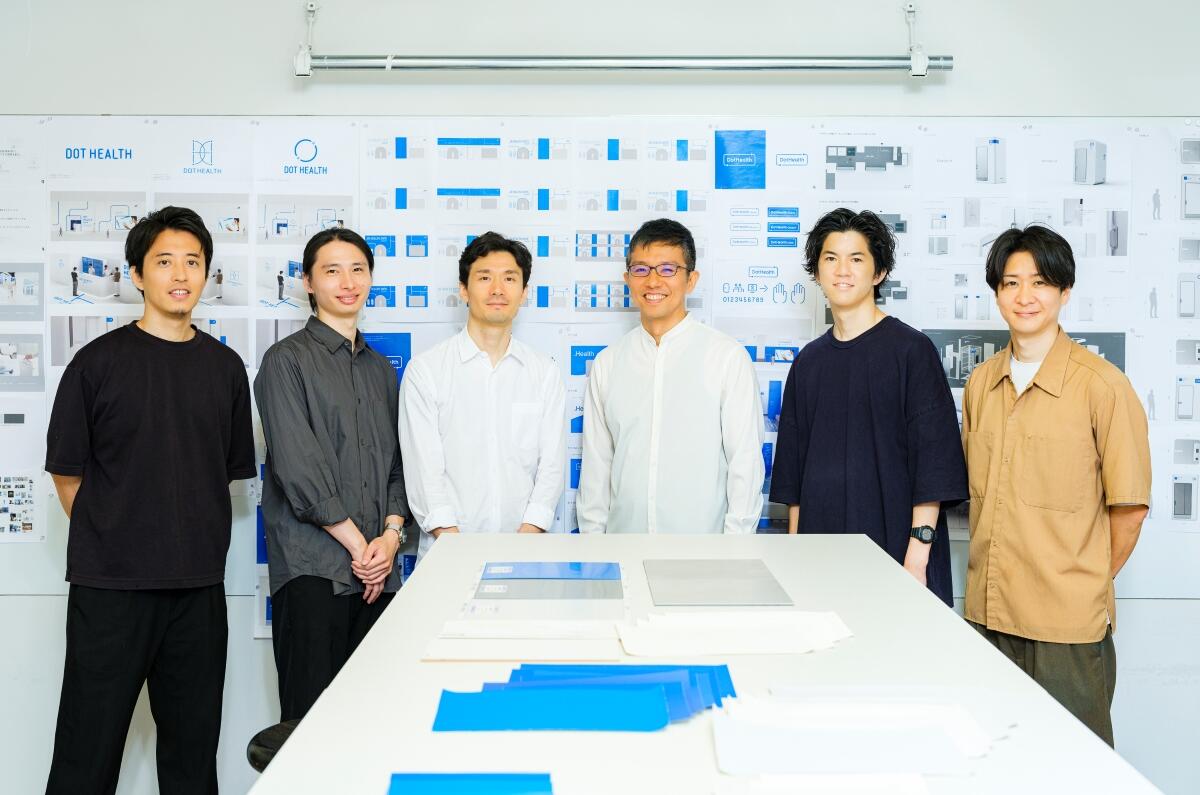
インハウスデザインスタジオ「MEDUM(メデュウム)」設立を通し、事業構想からプロダクト制作までの一気通貫した取り組みを強化している博報堂グループのスタートアップスタジオquantum(クオンタム)。
参考記事:「新規事業」や「プロダクト」を生み出してきたquantum、インハウスデザインスタジオ「MEDUM」によりさらなる進化へ(https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/news/topics/2025/01/5213.html)
そのquantumが、今回博報堂関西支社とタッグを組んで取り組んだのが、JR西日本のプロジェクト「DotHealth Osaka(ドットヘルス大阪)」「カラダ測定ポッドStation版」の開発だ。事業構想に込めた想いや、コンセプト/デザイン開発のポイント、博報堂グループ内の共創がどのようなシナジーを生んだのかなど、チームのメンバーに語ってもらった。
スピーカー
博報堂関西支社 岩宮 克臣 Chief Business Designer
博報堂関西支社 板垣 陸 Service Design Planning Director
quantum 執行役員 / Venture Architect 中村 覚
quantum Chief Design Officer 門田 慎太郎
quantum Industrial Designer/Art Director 北 海人
quantum Art Director/Graphic Designer 永井 創
生活者が日常の延長で健康管理できる空間を創出
――まずは、JR西日本のプロジェクト「DotHealth Osaka(ドットヘルス大阪)」「カラダ測定ポッドStation版」がどのようなサービスなのか、概要から教えてください。
岩宮
前段として、大阪は数多くの製薬会社が集積する場でもあり、博報堂関西支社としても、ヘルスケア領域を注力すべき事業領域としてとらえてきました。一方JR西日本は、コロナ禍をきっかけに、移動という目的がなくとも駅を利用してもらえるようなアイデアを模索していました。
こうした背景から、博報堂関西支社ではJR西日本とともに「ステーションヘルスケア構想」を掲げ、駅を基点とするセルフヘルスケアマネジメント支援に取り組んでいます。たとえば生活者が駅ナカで検査や診療を受けたり、エクササイズをしたり薬を受け取れるようにし、それぞれに紐づくさまざまなヘルスケア領域のステークホルダーを巻き込んだ新たなエコシステム構築を目指すという構想です。
板垣
その「ステーションヘルスケア構想」を具体的なコンセプトに落とし込んだ取り組みの一つが、「DotHealth Osaka(ドットヘルス大阪)」です。JR西日本の中核駅である大阪駅に、生活者が日常生活の延長で健康対策できる空間をつくり、まだ一般的に浸透していない各種ヘルスケアサービスの普及・実証ができるフィールドを立ち上げました。

空間内には「カラダ測定ポッドStation版」というマシンが設置されており、脳認知や髪、肌の健康状態を始め、実に何十項目もの健康データを取ることができます。特に女性の利用者に人気で、連日行列を作るほど盛況となっています。

――quantumとはどの段階から共創が始まり、どのような役割分担でプロジェクトを進めていきましたか。
岩宮
"街中で気軽に使うことのできるヘルスケア施設"というものは、現在なかなか目にすることはありません。ですから、「どういう空間・佇まいにするか」という点からしっかり定義しなければなりませんでした。硬いイメージで距離を置かれるのも、利用しやすい反面信頼度が低く捉えられることも避けたい。ブランディングやコンセプトメイクの段階からしっかりと固めていき、かつ生活者の体験価値のクオリティを担保するためにも優れたプロダクトデザインである必要がありました。
板垣
この案件は期間限定のキャンペーンではなくあくまで事業であり、舞台となるのは公共空間である駅のため、息が長く公共性の高いデザインが必要でした。そこで、事業デザインからプロダクト制作までを一貫して行うquantumに声を掛け、そのデザインチームであるMEDUMメンバーに参加してもらうことになったのです。博報堂関西支社の僕と岩宮さんが各事業のプロデューサー的な動きをし、MEDUMはデザインを、両者の橋渡しとしてquantum中村さんに動いていただくという座組になりました。

三者のキャッチボールから導き出した3つのデザインコンセプト
――デザインにおいて課題だった点やこだわった点はどこですか。
中村
まずは博報堂関西支社と一緒に作り上げてきたビジョンや目指したい方向性をデザインチームにインプットし、ゼロからデザインに取り掛かってもらいました。あらゆる検討事項が同時に進みつつ、日々変動していく事業開発プロセスだったので、いわゆるかちっとしたオリエンテーションを用意するのではなく、MEDUMチームと壁打ちを重ねる中で共に精査し、デザインの可能性を探索していくという、少し特殊な進め方を採用しました。

門田
そうでしたね。quantumと博報堂関西支社、JR西日本の三者が集まり、キャッチボールを重ね、最終的に3つのデザインコンセプトに落とし込みました。それが1.Innovative(イノベーティブ)、2.Accessible(アクセシブル) 3.Understandable(アンダースタンダブル)です。
1のイノベーティブというのは、JR西日本が提供する新たなサービスとして、耳目を引くような先進性を感じさせるということ。2のアクセシブルは、物理的にも心理的にも使いやすい、抵抗感なく利用できるデザインということです。3のアンダースタンダブルは、日常的に気軽に利用するものとして、装置や設備などどこに何があるのかわかりやすく使いやすいデザインにするということです。

北
私は、「DotHealth Osaka」の外観や内観、専用什器、そして「カラダ測定ポッドStation版」のインダストリアルデザインを担当しました。
プロダクトと空間の双方において、先に掲げた3つのコンセプトを踏襲しつつ、プロダクトそのものがシンボリックでありながら、空間の一部として調和するデザインを目指しました。
また、このプロダクトはサービスの中核を担う存在として、他の駅にも単体で設置されることが想定されていたため、単体でも人々の視線を引きつける必要がありました。そこで、ロゴ部分を中心にJR西日本のブランドカラーであるブルーを効果的に用い、視認性を高めながら、クリーンで信頼感のある印象を意識しました。

さらに、施工においては駅構内のため、半日以内で組み立てを完了させる必要がありました。そのため組み立てやすさ、搬入搬出のしやすさなど、裏側の工程も考慮しながらのデザインとなりました。
また、DotHealth Osakaは常設設備ですから、歩行者の足が当たりやすい下部は、汚れが目立ちにくいブルーの色面に。清潔感を演出する白は、空間の上部にレイアウトすることで、メンテナンス性と空間演出の両立を図っています。
永井
ロゴのグラフィックデザインにおいては、大勢の人が行き交う場所でもパッと目を引くデザインを目指しつつも、長年の利用を想定し、空間に上手になじむある程度オーソドックス感のある見た目でなければなりませんでした。結果的に、先進的かつ王道感ある、シンプルなロゴに落ち着きました。

門田
実は、お話をいただいた時点でJR西日本のブランドカラーである青を使おうと決めていました。JR西日本が行っている事業であるという事実がそもそも大きな強みですから、その関連性がはっきりと想起できるものにしたかったんです。この空間があるコーナーにも一面大きく青を使って、歩行者に「あの青い塊のある角」というふうに認知してもらうという狙いもありました。

中村
大阪駅は1日に約85万人が利用する巨大ターミナル駅で、「DotHealth Osaka」はその中央改札からほぼ30秒の場所に位置します。膨大な人と情報量のなかにあって、埋もれずに強い存在感を放つ場にすることができていると感じています。実際、待ち合わせ場所の目印にもなっている、といった話も聞きました。
板垣
当初、たとえば空港のように、外観はとがったデザインでも内部は徹底的にUXが練られて、ユーザビリティを追求したデザインが理想的だという話もしていました。結果的に想像以上のものになったと思います。
――本案件はMEDUMにとって、どんなチャレンジになりましたか。
北
駅構内に入る施設で、かつこの規模の空間デザインが初めてだったので、それ自体が非常にチャレンジングでした。規模がこれだけ大きいと、パソコン上でデザインしているときと実物を見たときとでは、自分が把握するサイズ感に大きなギャップが出てきます。印刷したロゴを手元で見ると少し大きすぎるように感じるのですが、現場に行ってみてみるとちょうどよかったりする。なので、実寸大に印刷した校正紙をオフィスに貼り、つねに実物のスケール感を意識しながらデザインしていきました。

中村
公共の場でもあるので、基本的には"誰も排除しないデザイン"がベースにありつつ、いかに最先端感を出すかが問われていました。3つのデザインコンセプトのうち、特にInnovative(イノベーティブ)とAccessible(アクセシブル)を行き来するやり取りが多かったかなと思います。先進的すぎると利用のハードルが上がってしまうし、親しみやすすぎる方向に触れると逆に信頼感が弱まってしまう可能性がある。皆でアイデアを練りながら、その繊細なバランスを探っていきました。
門田
駅構内ということで消防法上のルールもありますし、当然JR西日本としては安心安全を徹底して守らなくてはなりませんから、デザインに対しても厳しい目線で見られていたと思います。でも何か壁に直面するたびに、「どうやったら乗り越えられるか」と、非常に協力的でいてくれたのは心強かったです。
中村
博報堂関西支社の2人が我々の意図をしっかり汲み取ってくれ、JR西日本と共に建設的な議論を進めていってくれました。MEDUMチームも、デザインを出して終わりではなく、理想のデザインを実現させるために何度もやり取りを重ね、アイデアを出し合い、落としどころを探していってくれました。そうして各所が密に連携し、妥協せず進められたからこそ、実現までこぎつけられたのだと思います。
岩宮
JR西日本にとっても刺激的な体験だったようで、今回の事例を社内で共有したいと言っていただけました。また、不特定多数の人が行き交う関係上、駅構内の施設はしばしば破損したり汚されるといったことが起こるそうですが、「カラダ測定ポッドStation版」にはほぼそれが見られず、大変驚かれたようです。それだけ、この空間が何か特別な存在感をもって受け入れられているということ。それを可能にするデザインの力もすばらしいなと改めて感じています。
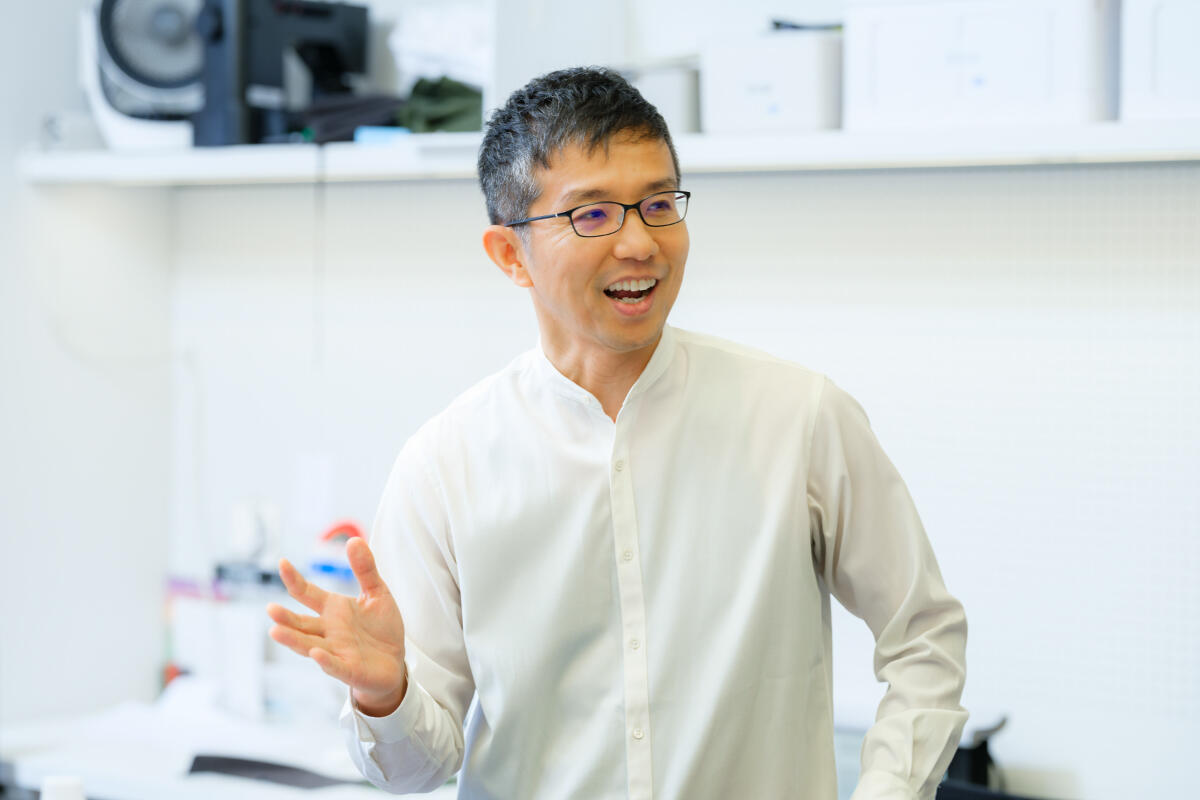
ヘルスケア領域から新しく大きなビジネスの潮流をつくっていく
――博報堂グループでタッグを組んだことによって、どんな強みが活かせたと思いますか。
岩宮
博報堂は、複雑で多様なステークホルダーが絡んだプロジェクトを、互いの事情を鑑みながら最適なプランニング、ソリューションにまとめ上げていくプロデュース力、マーケティング力を持つ会社です。これまで培ってきたその力は、ヘルスケア領域でももっと活かせるのではないでしょうか。というのも、人間の身体は変数が多く、解決策も変数が多い。言葉で表現できない納得感をどうつくるかが鍵になるからです。デザインを武器に、それをきちんと形にできるのが我々の強みだと感じています。
板垣
社外の実績あるデザイナーにこれだけのものを依頼するとなると、遠慮や忖度などから認識の齟齬が生まれてしまったり、思い切ったアイデアをぶつけられなかったりするでしょう。でも今回、同じ博報堂グループということで、デザインに関しても臆さずに意見を言うことができたし、それを受け止めてもらうことができたのは嬉しかったです。
中村
博報堂は、さまざまな企業と組んで壮大なビジョンを描くと同時に、ビジョンを実現する座組の構築をプロデュースしてきました。なので自然と事業の規模も大きくなるし、射程距離も長くなる。今回博報堂チームと協働することで、quantum単独ではあまり手掛けてこなかった規模感のプロジェクトを推進し、具体的に世の中にかたちあるものとして打ち出すことができ、非常に幸せな機会でした。

――今後の展望についてもお聞かせください。
中村
現在の「DotHealth」はあくまでも実証実験的な空間で、今後さまざまなヘルスケア関連企業に参画いただくことを想定しています。なのでまずはこの場所に、参画する価値を見出してくれること、すなわち、多くの方が体験に訪れること、この場所に活気をつくりだすことが重要だったわけですが、その第一段階は何とかクリアすることができたと思っています。ここを起点に、「ステーションヘルスケア構想」が少しずつ形になっていけばと思っています。
岩宮
今回、「DotHealth」というブランド含め、今後ヘルスケアを基点に多くのプレイヤーがつながっていけるデザイン構造をつくることができました。すでに、これまで接点がなかった方面からも含め多くの問い合わせが来ていますし、既に複数のヘルスケアプロジェクトが動き出しています。これから西日本を中心に、ヘルスケアという領域から新たに大きなビジネスの潮流をつくれるのではないかと思っています。
大阪・関西エリアに閉じないビジネス展開を目指して、新しいヘルスケア事業を大阪・関西で育み、良いものを全国に拡張していくヘルスケアエコシステムを構築していきたいと思っています。
門田
今後も博報堂グループ内で積極的にコラボし、事業やプロダクトの開発を行っていけたらと考えています。これまでの広告会社が何かを発信することのプロであったとして、今は事業を構想したり、ものをつくるフェーズにも力を入れていこうとしている。それぞれの力を掛け合わせることで、ビジネスを構想し、ものをつくり、そして発信するというセクションが連動し、より大きな動きをつくっていけたらと思っています。
中村
壮大な構想のもと、起点となる場所やプロダクトがプロトタイピングされ、具体的なかたちをもつことで、それを旗印として、人や会社が集まり、次なる展開につながっていく......。今回の案件ではこのプロセスをまさに実現することができましたし、この経験が、これから先にまたさまざまな新しい事業を生んでいく起点になるのでは、と思っています。博報堂には多種多様な事業の種や構想があると思うので、ぜひquantumでも実現化のサポートをさせていただけると嬉しいです。

岩宮 克臣
博報堂関西支社 Chief Business Designer
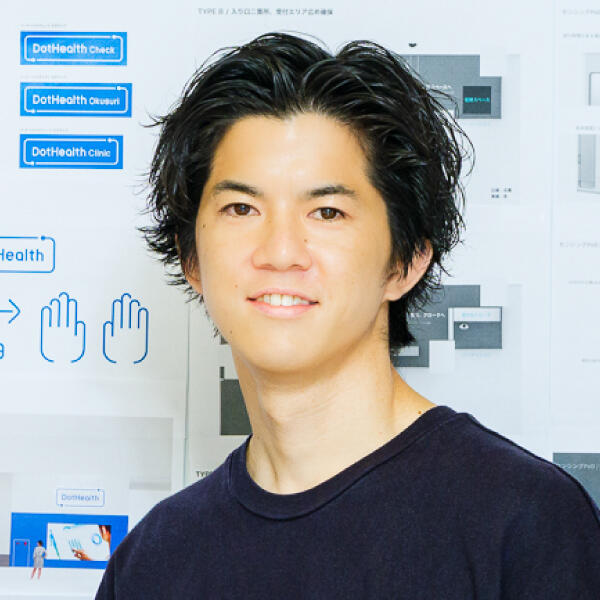
板垣 陸
博報堂関西支社 Service Design Planning Director

中村 覚
quantum 執行役員 / Venture Architect
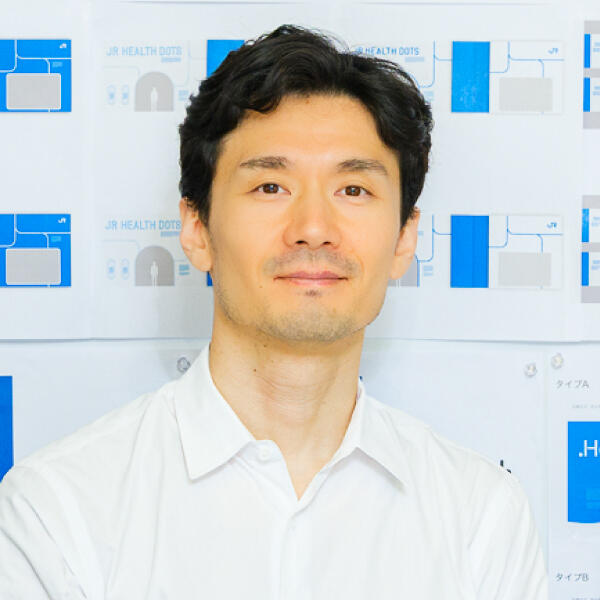
門田 慎太郎
quantum Chief Design Officer

北 海人
quantum Industrial Designer/Art Director
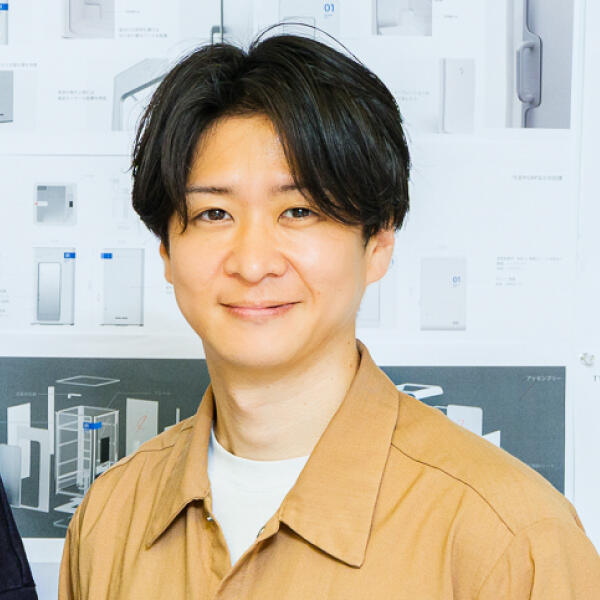
永井 創
quantum Art Director/Graphic Designer